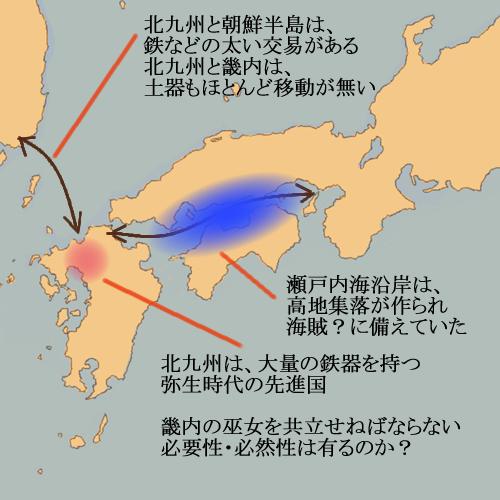|
西暦248年 9月 5日 午前8時 日本で部分日食 夜明け直後、東の空で、日本一帯で日食が見られた。 卑弥呼が死んだ年と一致し、関係が考えられる。 実は、この日に皆既日食が観測されたのは、 魏の首都、洛陽付近である 中国では、後漢の時代に日食の周期が知られていた。 魏の天文学者は、この日の日食を予測していたはずである。 卑弥呼の失脚の理由が日食なら、卑弥呼は大陸の暦を知らなかった。 大陸の暦を知っていれば、卑弥呼を陥れることは簡単である。 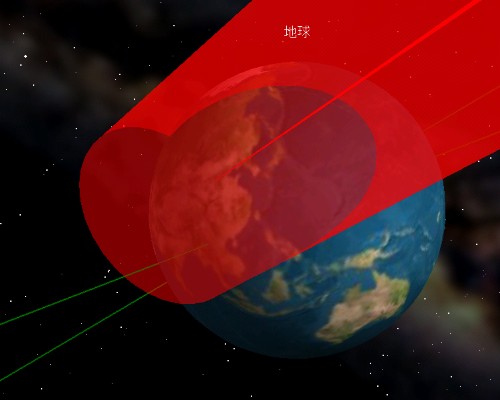 赤帯は、月の本影。 中心の赤い線の先で皆既日食が見られる。 (講談社ブルーバックス/太陽系大紀行2/太陽系シミュレーターより) |
日本神話で、アマテラスを天の岩戸に隠れさせた原因を作ったのは、
国津神のスサノヲであり、再び岩戸を開けさせたのは天津神達である。
太陽を祀る神=天津神
↓
太陽を意のままにできた
↓
日食を把握していた
↓
大陸の暦を知っていた
 つづき
つづき かおる
かおる