神社などに伝わる伝承では、
ニギハヤヒは、天火明命と、同一とされている。
天皇の皇祖神である天津神は、アマテラスとタカミムスビ。
その孫がニニギなので、天孫と呼ばれている。
ニニギの子孫が神武天皇。
この系譜上に、天火明命(アメノホアカリ)という神が登場する。
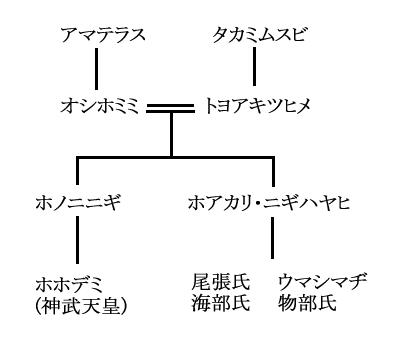
日本書紀では、天火明命は、ニニギの子とされ、
また、日本書紀一書(六)では、ニニギの兄ともされている。
ニニギに近い血筋であるとされている。
 みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを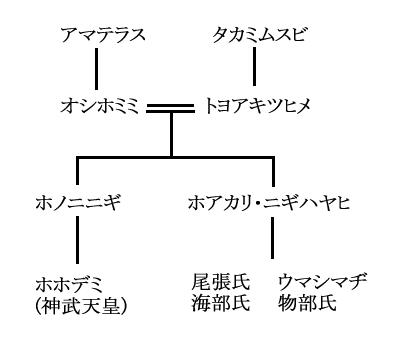
 にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを|
日本神話の流れ
イザナギ・イザナミが大八島を産んだ。
|
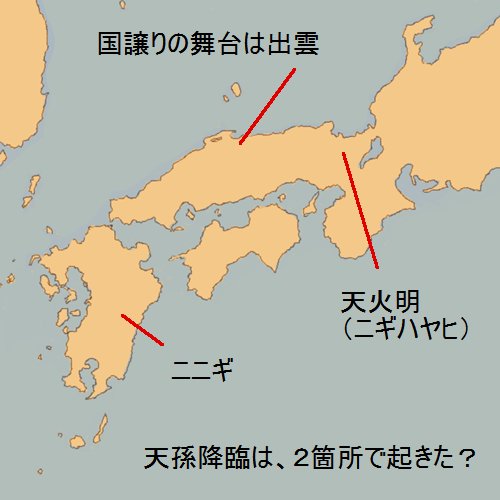
 にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを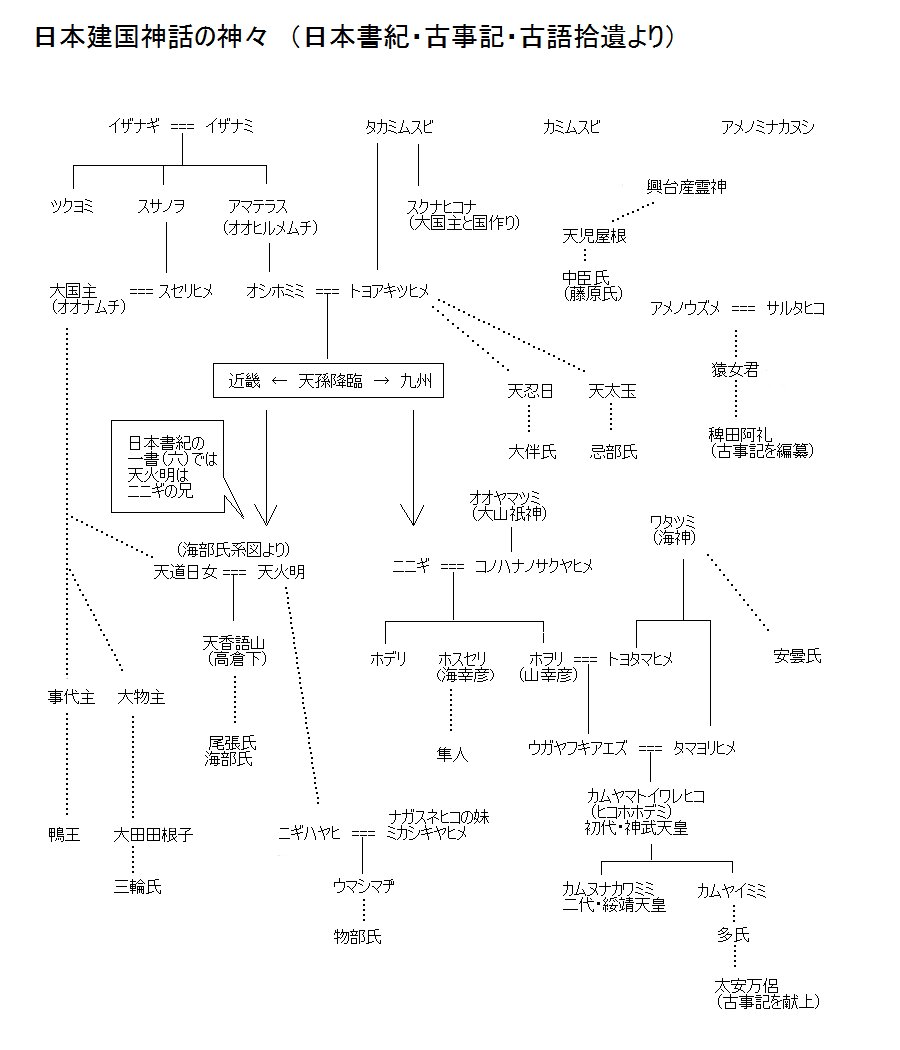
 にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを にい
にい みを
みを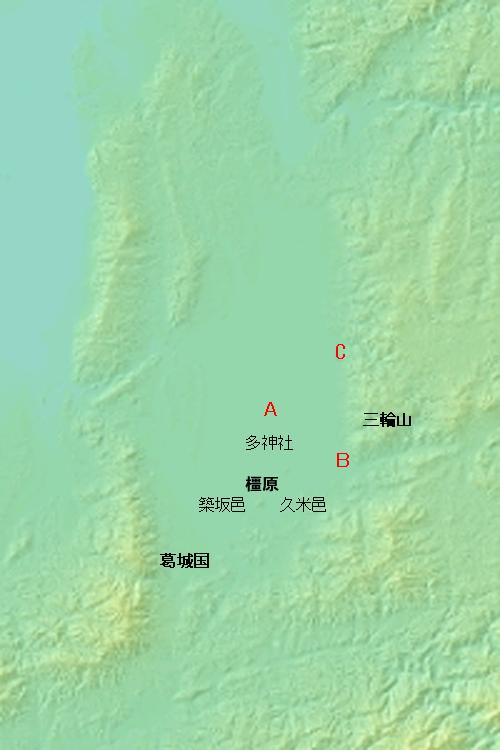
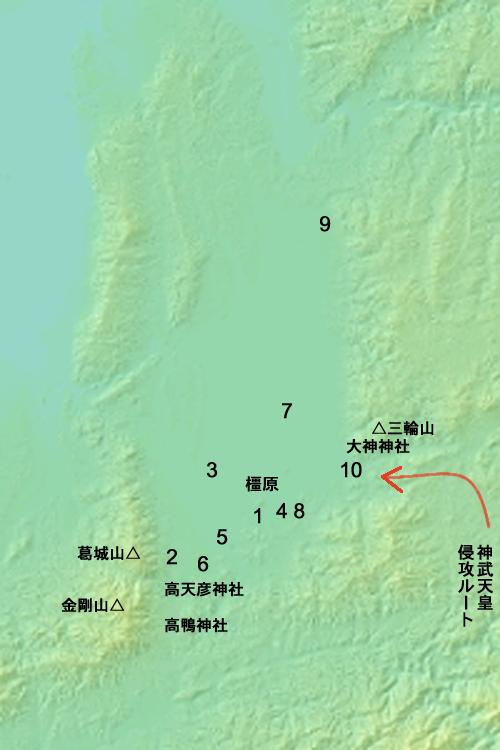 初代〜十代までの天皇の宮(位置は諸説あり大雑把です)
初代〜十代までの天皇の宮(位置は諸説あり大雑把です) にい
にい みを
みを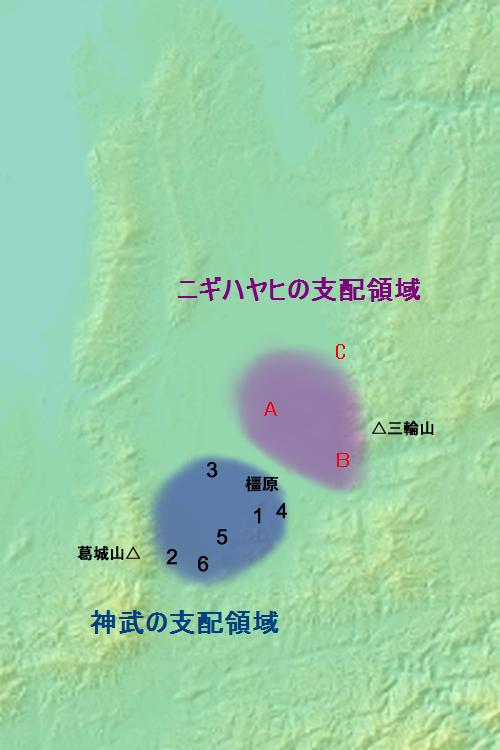
 にい
にい みを
みを